| Stuck In My Mind
|
||||
 |
これまでに使った 歴代デジカメレポ |
|||
| Find_Gratificational_One | ||||
私が一眼レフデジカメに望むもの それほどたくさんあるワケではありません。カメラ本体自体、だいたいが重いしデカいし。そこに交換レンズやストロボなどの周辺機器が加わればかさばるのは当然なのですから、便利とは言えません。今やコンパクトデジカメだって400〜500万画素はあたり前。800万画素にまで至っており、そこそこの性能を持っているですから、「そこそこ写って気楽に撮れればよい」だけならそちらを選びますし、実際それも平行して使っています。ならばその手軽さを捨ててまで何故一眼デジ?それを納得させるだけの要素が必要になります。 画質?しかしコンパクトデジカメを遙かに凌駕する画質など、プロ用しかありえません。本体のみでなく、高性能レンズ、大規模ストレージ、快適な画像処理を可能にする高性能パソコンなど、究極の環境が必要になります。 そこまで求めれば当然ながらコストがかさむ。クルマやバイクの改造と同様、限りなく金のかかる世界になってしまいます。 じゃあ一眼デジに何を求めるかといえば、自分の感性や表現したいイメージをどれだけ忠実に再現してくれるか、ということ。これこそがコンパクトデジカメとは一線を画す要素だと思われます。満足できるだけの「絵」が撮れれば文句はないのです。つまり「撮らされている」のではなく「撮りたいものが撮れる」こと。そのために私が求めているのは、レンズの大きさを生かしての描写力や解像力、起動の速さ、速写性能くらいなものです。 写真は昔から好きだったので、FILMカメラ経験も多少あります。当時使用していたのはNikonFE2、250mm付。その後仕事で画像を扱うようになったのですがFILMカメラではランニングコストがかかり過ぎる。そこでデジカメに頼るようになりました。発売になったばかりのデジカメの画質は現在のレベルから考えれば”論外”でしたが、それでも急激な技術開発競争のおかげでみるみるうちに高性能・低価格化し、「使える」ようになりました。 ここではその黎明期から手にしていたデジタルカメラについてレポートしています。 デジカメ選択で迷ったらこちらへどうぞ。 技術の進歩は日進月歩(秒進分歩?)ですから、次から次に発売されるモノを全部追いかけるワケには いきません。「どのカメラを選ぶか」ではなく「どう選ぶべきか」だと考えています。 (内容はあくまで私の主観に基づいています。あしからず)  |
||||
| メーカー・機種 | 撮像素子 | 画素数 | speed | メディア他 |
| SONY DSC-W1 (11台目) | 1/1.8型CCD | 530万画素 510万画素 |
30秒〜1/1000 | メモリースティック DUO, PRO, PRO DUO |
 |
選定にあたって | |||
| MZ3を失い、DimageXi が大失敗に終わった。発色がよく、ノイズが少ないサブカメラが欲しい。あくまでも気軽に使えること。メディアを含めて値段が安いことが条件である。CFカード使用機が流通しなくなった今、できればSDカード使用機が良い。でもそんなことにプライオリティを置くと失敗するから、あくまで大きなCCDであることにこだわってみた。W5に目を付けたのだが,基本性能が同じで価格が更に安い本機がお買い得だった。 | ||||
| 使用感 | ||||
| 発色が良いのはFinePixF10で決定だろう。F11が発売されたので実売価格は34,000円くらいまで下がっているが、メディアがxDピクチャーカード。う〜む、これは持ってないぞ。だってこれって悪名高いスマメの後継メディアだろ?やだなー、壊れやすいんじゃないか。本体価格とメディアがネックとなって二の足を踏む。 雑誌を見ていて気が付いた。ノイズが少なくカラーバランスに優れているのはSONYのDSC-W5とCanonのPowerShot A610だ。まてよ、両方とも500万画素1/1.8型CCDじゃないか!他の500万画素機はみィんな 1/2.5型CCDを使ってる。ほ〜ら、やっぱりCCDはでかい方がいいんじゃないか♪ 正直なところ画素数なんて500万画素も要らないんだけど、現在ではそれ以下が選べない。300万画素クラスではおもちゃカメラになってしまうから、これでいい。んで価格コムで調べてみると、おおっ、W1っちゅうのがあるんだね。基本性能はほぼ同じでW5よりも更に5,000円ちかく安いぢゃないか。SONYだからメディアは当然メモステなんだが、幸いパソには”何でもカードリーダが付いてるからもーまんたい。うん、これでいいや♪ 良いところは3つ。1つ目はとにかく安かったこと。ブラックボディしか在庫がなかったけど実物はいい感じだし、筐体が大きめかと思いきやMZ3より小さい。 2つ目は単3電池駆動であること。だって電池切れで泣くことが絶対ないじゃんw。専用電池は思いっきり長寿命じゃなけりゃダメです。 3つ目は(まだ使ってないけど)動画がMPEG30フレームであること。MZ3も”動画デジカメ”だったが、何せAVIファイル。データ量が膨大なクイックタイムムービー再生です。編集が大変だったことが気になっていた。でもこれならデータ量が少なくて済むんじゃない?そりゃCASIOのMPEG4機とは勝負にならんだろうけど。ちなみにCASIOのMPEG4ってキレイだよ〜。すんげー滑らか♪物欲がぐらぐら来た。でも、Petit-nameに「何の機能が欲しいの?」って聞かれてやっと思い留まりました。 画像はコントラストが強い。うん、やっぱSONYだ、ってカンジの処理。ノイズはまるで無し!これは嬉しい。色はMZ3に及ぶべくもない。でも22,800円ですからね。許せちゃう。 レスポンスはグッド。起動、合焦、画像処理ともに速く、ストレス無し。いや、500万画素は再生に時間がかかる。 それを誤魔化すため、先に荒い画像を出して騙しといて後からゆっくり高精細画像を読みだしているカンジだ。上手いじゃないですか〜、SONYさん。いいのよー、許しちゃう。最新機種じゃないんだからそんなの想定内です。 |
||||
| 10台目 MINOLTA Dimage Xt |
1/2.7型CCD | 330万画素 320万画素 |
4秒〜1/1000秒 | SDメモリーカード |
 |
選定にあたって | |||
| とても気に入っていたDSC-MZ3を、夏の東北旅行で水没させた。それで仕方なく新潟のソフマップで見つけ即買いしたのがコレ。¥10,000なら文句ないでしょ。選択の余地はない。とりあえず買うしかない、というのが購入動機だった。中古品だし、多くを望む方が可笑しい。256MBのSDメモリーカードが¥4,000。小さくて軽いし、気軽に撮るにはこれで十分・・・と割り切ったはずなのだが。 | ||||
| 使用感 | ||||
| デジカメ10台目。 発売になった頃なら数値上の性能と携帯性は優れていた。屈曲型の光学系を用いてレンズの出ない×3Zoomを実現しているから、とても薄くて軽い。デザイン性にも優れている。そう、このデジカメは「初めにデザインありき」で開発されたと思えば納得がいく。 でもはっきり言って”ハズレ”。強すぎるコントラスト、不自然なエッジ強調、合焦エリアの狭さ・・・当時の画像処理技術水準ではコントロールしきれないほど”不出来”なCCDだったのだろう。 1/2.7型CCDで330万という極小画素では話にならん。ほんの一瞬で捕まえたほんのわずかな光を処理しきれないまま製品化してしまったんだろう。それで市場に投入したのは、だから「初めにデザインありき」というコンセプトを強く感じるのだ。写りが良いはずはない。画像を見ても幸せになれない。だからこんなの写真じゃない。 「薄く、軽く」。カシオがそれを実現しちゃったから、カメラメーカーとして意地があったのかも知れない。あるいはIXYのデザイン路線が成功したからなんだろうけれど、「薄く、軽く」したことでバッテリーも小型化せざるを得ず、40枚も撮れやしない。専用バッテリーだから電池が切れたらその日の撮影はおしまい。 「薄く軽く」するために装備できるボタンの数を減らさなきゃいけない。だからセルフタイマーさえ階層深くに押し込められてしまった。みんなが笑顔でいるうちに「はーい、撮りますよー」って言えやしない。 本体が小さいんだから、レンズがその位置では指がかぶっちゃうじゃないか。それにカメラを構えたところと、イメージしたところとで画像がずれてやんの。 イメージ通りに撮りたかったら、50cm右にずれて立たないとダメです。なんと使い勝手が悪いことか。 結論。こんなのカメラじゃない!おもちゃカメラだったらこれでけっこう。でもミノルタなんだからこそ許しちゃいけない。すべてが「パッケージング」のために犠牲になっている。 |
||||
| 9台目 Nikon D70 |
23.7×15.6mm 原色CCD |
630万 | 1/8000 | CF マイクロドライブ |
 |
選定にあたって | |||
| 選択肢は3つだった。Canon EOS20Dは800万画素C-MOSセンサー。もう一台はFUJIのFinePixS3Pro。1260万画素ハニカムCCD。一眼デジはレンズやストロボその他周辺機器に金がかかる。しかし予算に限りがあるので本体が高価なモノは残念ながら手が出ない。レンズ群を揃えてしまうと、他のメーカーに移行することはなかなか難しい。一眼選びはメーカー選びになってしまう。第一希望はFinePixなので、今回は同じレンズマウント方式のNikonとした。 | ||||
| 使用感 | ||||
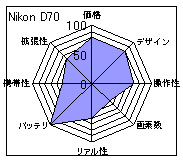 手に持った感じはしっくり馴染む重さである。本体各部のプラスチックから高級感は漂ってこない。コンパクトデジカメから乗り換えたばかりなら胸躍るかも知れないが・・・。大きさはist-Dよりはるかに大きく、D20よりやや小さい。画素数が購入を迷わせた要因の一つ。これから数年使うことを考えると、630万画素にアドバンテージは無いからである。D20の800万画素が最低ラインだったかも知れない。メディアは安全性・信頼性が高いCFでgood!ただし最高画質のRAWモードでは100枚撮れない。本体付属の「Nikon
View」で現像のみ可能。それ以上のレタッチにはそれなりのソフトが必要なのでここでも出費が求められる。画像をその場で確認しようとすると、RAW+MサイズJPGの同時記録を選択する必要があり、そうなると1Gメディアでも撮影可能枚数は更に減ってしまう。 手に持った感じはしっくり馴染む重さである。本体各部のプラスチックから高級感は漂ってこない。コンパクトデジカメから乗り換えたばかりなら胸躍るかも知れないが・・・。大きさはist-Dよりはるかに大きく、D20よりやや小さい。画素数が購入を迷わせた要因の一つ。これから数年使うことを考えると、630万画素にアドバンテージは無いからである。D20の800万画素が最低ラインだったかも知れない。メディアは安全性・信頼性が高いCFでgood!ただし最高画質のRAWモードでは100枚撮れない。本体付属の「Nikon
View」で現像のみ可能。それ以上のレタッチにはそれなりのソフトが必要なのでここでも出費が求められる。画像をその場で確認しようとすると、RAW+MサイズJPGの同時記録を選択する必要があり、そうなると1Gメディアでも撮影可能枚数は更に減ってしまう。私はデジカメの撮影可能枚数を最低100枚(フィルム3本以上)と考えている。何故ならば連写であっという間になくなってしまうからだ。 連写はJPGのみで秒3コマ。”144コマまで”というが一応メディアの限界までは撮れる。しかし11コマ目あたりから急激に速度が落ちる。これはフルサイズでもそれ以下のサイズでも変化無し。また80倍速CFでもマイクロドライブでも同じだった。秒3コマはスポーツ写真には厳しい数値だ。バイク走行を撮る場合には秒5コマは欲しいから、ここでもD20がうらめしい。 バッテリーは超優秀で1000枚以上撮れるから問題なし(ただし専用リチウム電池だからなくなったら終わり。もう1本購入しておくorCR電池3本と専用ケースを持ち歩く必要がある)。 起動0.2秒に不満なし。合焦速度もD20に比べるとほんの少し劣るか同程度で優秀。操作性は先代のE10より良くないが、できることの多様性を考えると許せる。ダイヤルや各種ボタン等のインターフェイスは所有欲を満足させてくれるレベルだが、設定画面がやや子どもっぽくチープな印象で、そのアンバランスさにがっくりする。EOS Kiss Digitalを食うための入門〜中級機なので仕方がないが、先代のE-10に比べると高級感や所有する喜びは劣る。 同時購入したNikon SpeedLightが秀逸。ワイヤレス発光が可能なのだ。本体装着時はポップアップストロボが使えなくなるが、ワイヤレスで使えば光量は増大する。更に別角度からの照射が可能だからポートレート撮影などでは非常に立体感のある自然な画像が撮れる。これは”買い”だ。 一眼デジなのだから当然レンズ交換をせねば意味がない。でも純正レンズ群はメチャメチャ高価だ。全域F2.8ととても明るい18〜35mmと28〜300mm2本で50万円!サードパーティにリーズナブルなものがあるのでそれらを購入する予定だが、そうなると18〜70mm付のD70キットではなく、カメラ本体のみ購入したほうが賢明だったかも知れない。そこまできちんと調べれば良かった。 ’04 12月のミレナリオはこちら→  |
||||
| 8台目 SANYO DSC-MZ3 |
1/1.8型 プログレッシブCCD |
200万 ×3 Zoom |
1/2500 (静止画) |
CF マイクロドライブ |
 |
選定にあたって | |||
| COOLPIX775を人に強請られたのでE10の補助機として購入。豊かな色表現と動画撮影が可能。非常に魅力ある機種で、現在でも”名機”と言われている。既に後継機種が発売されていたので価格は3万円を切っていた。QuickTime Movieで動画デジカメと銘打つほどだからメディアを奢らなければならない。IBMマイクロドライブ1Gを同時購入したが、メディアの方が高価だった。 | ||||
| 使用感 | ||||
| 大きなCCDを用いて発色が豊かで素晴らしい(拙のページの画像は殆どMZ3で撮影している)。秒30fの動画が撮れること。この二つが本機の大きな魅力。コンパクトデジカメとしては重量級の部類に入るだろうが、ほぼ全面ステンレス製の外装には高級感がある。SANYOは”動画デジカメ”としてのシェアを確立していたが、それはVGA30f/secを実現していたからだ。 秒30フレームといえばTVと同じ。ビデオ並みの高画質だ。当時他メーカーは大抵秒15コマの15秒〜30秒程度が限度だったのだ。それにメディアの限界まで撮影可能だ。ファイルはバカでかくなるが綺麗ならそれで納得。ただし他ファイルへの変換をするときは320×240dotに落とされてしまう。VGAのままAVIやWMAに変換するにはソフトを別途購入する必要があるのは納得できない。 起動も合焦速度も記録速度もメチャメチャ遅いが、私の場合、それらを求めるならE10があるので気にならなかった。200万画素だから、A4プリントに耐えられない程度の解像力でしかないが満足度は非常に高い。これでスキーの滑走シーンやバイクの走行シーンなどを撮りまくり、フォームチェックを行った。 2年間思い切り使い倒してきたが、ここに来てガタが出始め、ピンぼけしやすくなったしバッテリーの保ちも悪くなった。首から下げてバイクで走ったりスキー場で転んだりしていればそれも当然なのだがw。 時折システムエラーが起きてウンともスンとも言わなくなる。そんなときはバッテリーをいったん抜いてさし直せば復活する。64MBメディアで約100枚撮影可能。 愛着が湧く一台である。 ’05年8月 秋田の温泉で水没、お亡くなりになりました。合掌(ち〜ん) |
||||
| 7台目 OLYMPUS E-10 |
2/3型原色CCD | 400万 ×4 Zoom |
1/640 | CF スマートメディア |
 |
選定にあたって | |||
| 北海道で景色の写真ばかりを撮っていたときは良かったのだが、動いているバイクを撮ろうとしたとき、シャッターのタイムラグが問題になった。いくら撮ってもフレームに収まらないのである。この”レリーズラグ”を克服するには一眼デジしかなかった。購入してみるとたくさんの不満があることに気がついた。しかし私は使用目的が明確だったからこれでよい。一眼デジ入門機としては満足度が非常に高い。 | ||||
| 使用感 | ||||
| オリンパスは妙に好きなのである。初めての400万画素機に期待したが、それは裏切られなかった。A4フルサイズ出力に十分耐え、毛穴まで見えるほどの解像力にワクワクした(現在のレベルじゃあたり前だけどねw)。シャッターチャンスに強い。それだけで購入した甲斐があった。発色はオリンパスらしく控えめなうえに、変にエッジ強調などもないので自然な中にもキレのある絵づくりが可能だ。メディアは何故かCFとスマメの2枚差し。撮影画像をどちらに記録するかボタンとダイヤルで簡単に選択が可能。メディア間でファイルのコピーが可能だが、その意味がよく分からなかった。 背面の液晶モニターは水平までの上方向に2段、角度をつけることが出来るため、極端なローアングル撮影も得意だ。下方向には1段なので、上からの撮影には限界があるけど、これのモニターによって面白い絵づくりが可能だった。 問題点は列挙すればキリがない。デカくて重くてかさばる。バッテリーの保ちが極端に悪く単3ニッケル水素4本がすぐ無くなるから、3セットは持ち歩かなくてはならない。一眼レフのくせにレンズ交換が出来ないのは、CCDにゴミが付くのを嫌ってのことらしい。事実、フォーサーズ・システムになった現在のオリンパスはCCDの前にホコリをブルブルふるい落とすギミックを装着している。×4Zoomを広角側にふっているのでそれは良し。×1.3程度のテレコンが付くがズームは使用できなくなる。 最大の問題はシャッタースピードが遅すぎること。1/640では話にならん!絞り優先オートでのダイヤル操作がとってもやりやすいのは良いのだが、慣れないうちはいつも白トビしていた。明るい太陽の下などでは注意が必要。 恥ずかしい話だが、集合写真を撮るときなどにタイマーを使うといつも白トビしてしまう。何だかな〜と、しばらく理由が分からなかった。その後、レンズなどの仕様変更はないまま500万画素のE20が発売になったが、画角が変わった分使いにくくなったような気がして欲しいとは思わなかった。長く使っていてこのカメラのクセがやっと分かる。愛着が湧く一台である。 RAWモードって何?一回も撮ったことがないw。 |
||||
| 6台目 Nikon COOLPIX775 |
1/2.7型CCD | 200万 ×3 Zoom |
不 明 | スマートメディア |
 |
選定にあたって | |||
| 動画が撮りたくて本機種を選択した。とはいっても秒15フレームで15秒程度しか撮れない。一番の購入動機は「一度はNikonを使ってみっかな」というだけだ。安かったしw。 |
||||
| 使用感 | ||||
| 購入は失敗だったとは言わないが、愛着はぜーんぜん湧かなかった。プラスチックボディだから軽くていい。それにメディアがCFだから資産が継承できる。でもいかにも安物で所有欲は満たされなかったし、画像も感動がなかった。軽さ以外はKODAKの方がはるかに良かったなー、って感じた。バイクで持ち歩いていて「壊れてもいいや」ってなノリで使っていた。 バッテリーは専用リチウム。この専用電池ってのは不便です。だって予備バッテリを購入して持ち歩くか、電池が切れたら撮影を諦めるしかないんだもの。予備は8000円もする。電力消費が少なく、単3が使えるものがベストですね。現在、原因不明のまま不動品になり、お蔵入り。落としたからかなw |
||||
| 5台目 KODAK DC280Zoom |
不明 | 230万 ×2.5 Zoom |
不 明 | CF |
 |
選定にあたって | |||
| もちろんKodakだから色には期待してましたけど、こんなに小さなレンズで綺麗なワケねーなーと思いつつ、壊れないことがいちばんさ!アメリカ人が使うモノなら丈夫だべ。それだけで選んだ一台。デカくて重いのはご愛嬌。CFだしw。なかなか良かったです。 | ||||
| 使用感 | ||||
| バイクで持ち歩いていると、カセットウォークマンにしてもMDプレーヤーにしても長期間の振動でガタガタになりネジが抜けちゃったりした。デジカメってのは精密機械だからこれも当然なんだけど、どうも不具合が出てくる。壊れないヤツはないかと調べてみたけど、雑誌にもサイトにも「耐久性」に関する記述は見つからない。クルマで言えばアメ車がいちばん頑丈なのだから、大雑把なアメリカ人の使用に耐えるものが一番良いだろうという判断でこれを購入した。事実、つくりは良かった。ファニーなデザインは伊達ではなく、グリップ部と底面のゴムは好感触だし座りも良い。 発色はコダックらしく派手な色が出る。肌色も赤も空の青も素晴らしい。何より失敗が一枚もありませんでした。楽しい絵が撮れるという点では歴代いちばんではないでしょうか。デジタルズーム付の×2.5Zoomではやや不満でしたが。 ソフトケースに入れたままバイクで走行中に落っことしても壊れない!さすがアメリカ製ですこと。凄いねっw。でも2回目に落としたら電池ケースのふたがユルユルになってしまった。ヨドバシに持ち込んだら、別の店で購入したのに保証期間内だからとクレーム扱いで交換してくれた。なんてステキなお店でしょう。感謝してます。 |
||||
| 4台目 OLYMPUS C-2020 Zoom |
1/2型 CCD | 200万 ×3 Zoom |
不 明 | スマートメディア |
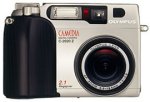 |
選定にあたって | |||
| 200万画素あれば使えるだろうと思い、高かったけど飛びつきました。この頃から既に画素数競争が始まっていたように思います。C1000Lに比べたら格段のコンパクトさも魅力でした。当時はやはりオリンパスが一歩先を行っていましたから、迷うことなく購入。 | ||||
| 使用感 | ||||
| 200万画素時代の幕開けとなった機種。やっとFILMカメラ肩を並べ、「使える」時代が来たと思いました。それまで開発者側には、「デジカメは銀塩カメラとは違うんだ」とでもいうような変なこだわりがあった気がしますが、本機種はそこからカメラに回帰した一台だと思います。気軽に撮れて画質もそこそこでしたが、白トビしやすいし、ズームをかけると狙った画像が下半分しか写らない。アキバの怪しい店で買ったのでひょっとしたらB級品だったのかも知れません。これもメディアがスマメでしたが壊れやすかったですねえ。 | ||||
| 3台目 OLYMPUS C-1000L |
1/2型原色CCD | 85万 ×3 Zoom |
1/10000 | スマートメディア |
 |
選定にあたって | |||
| 100万画素と85万画素の2機種がありました。いよいよ画質が追求できる時代になってきた頃の製品です。でも高かったなあ。レンズが大きいので質の良い画像が撮れるだろうと思って買いました。ホントは勿論画素数の多い方が良かったのですが、何せ高かった。それでもやっぱり「基本がカメラ」でできたデジカメだった。電機メーカーよりもカメラメーカーに一日の長があると感じた一台です。 | ||||
| 使用感 | ||||
| フルオートでシャッター押すだけ。それでもそこそこ見られる画像が手に入る・・・なかなか楽しい機種でした。画素数なりの画質になってきて、デジカメはこれからも発達していくんだろうなあという予感を持ちました。ただ当時のオリンパスは消費電力がデカくて閉口しましたね。 当時のスマメはCFよりは少しだけ安かったのですが、壊れやすいのが痛かったな。抜き差ししているだけで壊れたモノです。だから私はいまだにCFの支持者です。ガタイはデカいのですがプラスチックボディなので軽い。高級感まるで無しw。 未来的なデザインに惹かれてこれを買った人は多いのではないでしょうか。でもカメラメーカーでさえ、デジカメがカメラの範疇に入れて良いのかどうか迷っていたような気がします。 |
||||
| SONY DSC-F1 | 不明 | 35万 ×3 Zoom |
1/7.5〜1/1000 | 内蔵8Mメモリ |
 |
選定にあたって | |||
| これは購入したのではなく、職場にあったものです。 | ||||
| 使用感 | ||||
| FILMが要らない、パソと繋ぐことができる、小さくて持ち運びがしやすいというデジカメの基本を押さえた製品。レンズがぐるぐるする利点は分かりませんでした。電器メーカーが作るとこうなるってコトだったのかな。30万画素だから画質は推して知るべし、といったところ。 | ||||
| CHINON ES-3000 | 1/2型 CCD | 41万 ×3 Zoom |
不 明 | 内蔵1Mメモリ 1995/12発売 |
 |
選定にあたって | |||
| フィルム代、現像代のかからないデジカメ。素晴らしいっ!飛びつきましたね。コダックDC-50のOEMだと思われる。たかが41万画素だから写りに期待などしなかった。でもカシオのQV10(30万画素)よりはマシだろうと。ただただランニングコストがかからないことだけで購入した。10万円近い価格だったから、はっきり言って失敗だったかも知れない。 | ||||
| 使用感 | ||||
| プラスチックの安っぽくてバカでかいボディ。液晶モニターなんか付いてないから、撮ったその場で画像を確認することも出来ない。バッテリーも内蔵式でいつ切れるか分からない。それでもFILMが要らないという理由だけで存在価値はあった。選択の余地なんて無かった。画質がどうのなどと言っていられないが、サービスサイズ程度ならなんとか耐えられる程度。 内蔵1MBメモリでは5枚しか撮影できない。1枚当たり200KB弱。パソがまだMS-DOSで動いていたり、やっとWindows95が出回ってきた時代です。HDDはやっと200MBクラスが一般的になってきた頃です。USBなんてあるはずもない時代だったから、パソとはシリアル接続で読み込む。遅せ〜! PCMCIAカードメモリスロットが付いていたが、メディアがメチャメチャ高かったから買えなかったし。 デジカメの黎明期、こんなのもあったという笑い話になってはいる。 |
||||
| デジカメと この先どこまで 行くのやら・・・・おそまつ | ||||